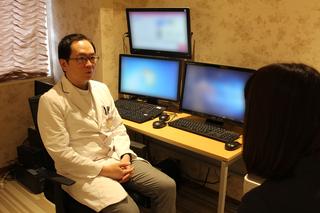目次
——透析治療をマラソンに例えると、患者さんがランナーなら、医師は伴走者のような役割なのでしょうか。
伴走というよりは、タイムキーパーのような役割かもしれないですね。5km、10kmと、各地点でランナーの走りぶりを見守る立場です。透析は、患者さんご自身の努力とよく言われるんですが、やはり、最初からスピードを上げたくない人もいたり、スタートは切ったものの「やっぱりやめたい」と、途中で棄権したいとおっしゃる人もいるんですね。実際、「透析をやめさせてください」という話は、まわりに他の患者さんがいらっしゃるときでも、回診中に時々受けてきました。
——でも、やめたら……。
遠からず尿毒症に陥り、残念ながら命を落とします。慢性透析、つまり生涯続く透析治療は、終末期の一部の場合を除いて、自発的に「やめる」という選択肢はないということをお話しています。
私はもともと、腎臓病全般を診る腎臓内科が専門です。長年の印象としては、透析はそのうち2割くらいの分野なんですね。残り8割の病気のなかには治せたり軽快する腎臓病も結構あるんですけど、治せない末期腎不全を専門に日々担当するというのは、やはり医師としてのジレンマが消えないところもあります。
この患者さんは、ある時期に透析が必要になったけれども、もっと何年か前に腎臓病に気づいて治療していたら、透析にまでは至らなかったんじゃないか……と思えるケースもあるわけです。腎臓病全体を知るだけに、透析治療の難しさを感じざるを得ない。
——ジレンマを抱えながらも、この道を歩み続けるモチベーションとはどんなものでしょうか?
究極的には、これまでに診てきた患者さんへの倫理的な責任感からです。これだけ、亡くなる方が多いということがわかっている治療分野で医療行為をしているわけですから、これまでに担当した方々やご家族に恥ずかしくない仕事をしたい。
透析治療は、患者さんと過ごす時間が非常に長いんですね。血液透析は1回4時間。私はずっとその間、透析室にいます。「これから始めます、頑張りましょう」というところから、終わって「また今度」というところまで患者さんと一緒なんですね。医療にはいろいろな治療がありますが、外来で、患者さんとここまで同じ時間を長く過ごす治療はないと思います。
一方で、医師としての姿勢がそのまま反映されてしまう治療でもあります。型どおりに透析の回診をして、あとは熟練の看護師さんや技師さんに任せて、医師なりの業務効率を上げようと思えばできるんです。しかし、先ほども言ったように、透析は「死」にいつも近い治療でもあります。そういう方々への治療に、医師都合の業務効率を求めたくはない。大変ではありますが、その姿勢で、ずっとやってきています。

——宮本先生は代々医師の家系で、お祖父様やお父様は外科医でいらしたそうですね。内科ならではのやりがい、面白さというものはありますか?
患者さんと会話する時間が長くとれるという面では、内科に進んでよかったと思います。
医師2年目の秋、まだ初期研修医だったときに病棟の看護師長から言われた言葉があるんです。私は正直に言って、出来のよい研修医ではなかったので上司によく怒られていたのですが、その看護師長が「宮本先生は患者さんの話をよく聞いていますね。みなさん、喜んでいますよ」と何気なく褒めてくださったんです。そのとき初めて、医師は“人に喜ばれる仕事”ということをプロとして意識したんです。思えば、それが内科医の道を選んだ直接のきっかけだったかもしれません。何科でも大変なのは分かったけれど、それなら言葉で患者さんと向き合える分野がいいなあと。
初期研修医時代は、本当によく院内で泣いていました。怒られてつらい、疲れてつらい、寝られない、家に帰れない。そして何より、信頼してくださった患者さんがご病気で亡くなる。がんで若くして亡くなった患者さんが自宅へお帰りになり、空っぽになった病室に行って一人で泣いていたこともありました。その精神的な負担から、泣けなくなったら医師を辞めようと決心していた時期もありました。
ところが、医師を続けていると、やがて「泣いている暇なんかない」ということに気づくんですね。それを教えてくれたのも患者さんかもしれない。よく、医師の世界では「患者さんに学ぶ」と大原則をうたうのですが、実感としては、「学ぶ」というより「育てていただく」という感覚です。
やっぱり、私の医師としてのやりがいは、患者さんの存在なしには語れません。仮に天国というものがあったとして、いつかそこで担当していたみなさんと再会したとき、恥ずかしい思いをしないような仕事を今後もしていきたいですね。
透析内科 柴垣医院 自由が丘